半導体産業を牽引してきた「ムーアの法則」とは?!
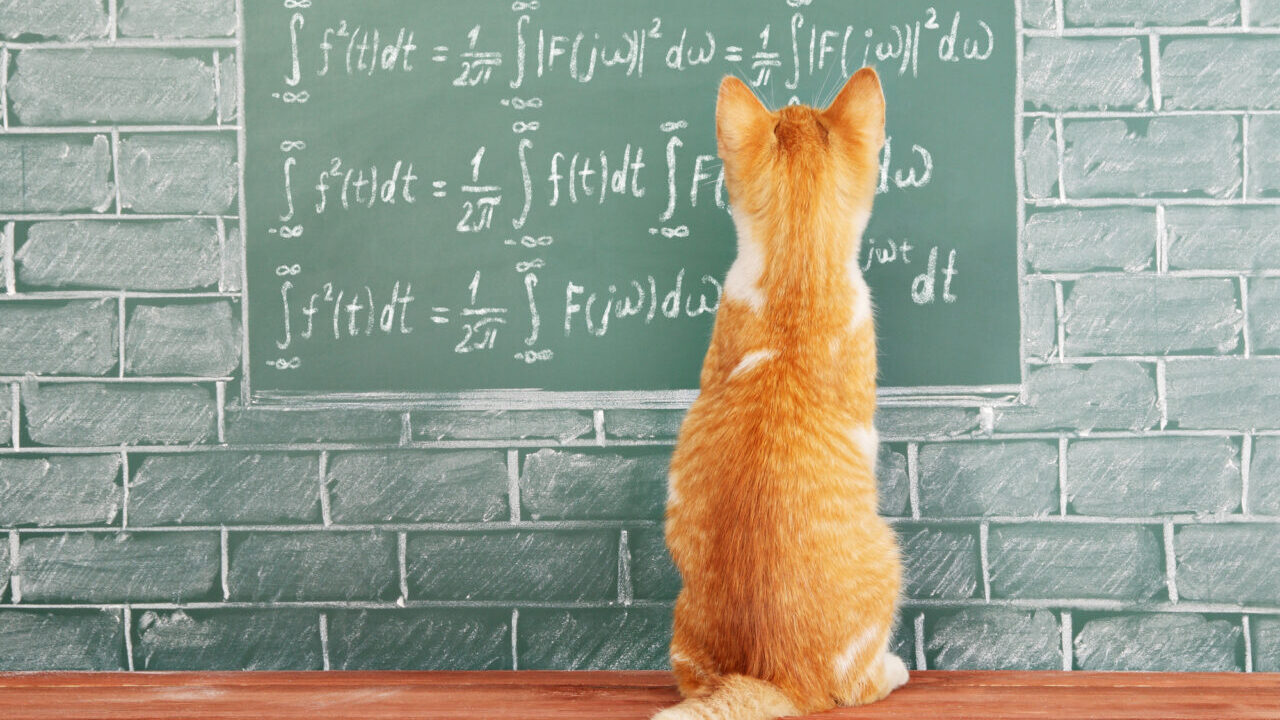
ムーアの法則とは、1965年にゴードン・ムーア氏が提唱した『半導体の性能が『18か月で2倍になる』という法則です。半導体産業を牽引してきたムーアの法則や、影響を与えた半導体集積回路(IC)の進化など併せて解説していきます。
はじめに
「ムーアの法則」の公式は、「p=2n/1.5」(p=倍速・n=年数)です。この法則は、1965年にゴードン・ムーア氏が自らの論文の中で、経験則として発表したものです。インターネットで検索した際に見かけたことがある方や、なんとなく知ってはいるという方も多いでしょう。
しかし、法則と聞くと難しく感じることや集積回路(IC)といった半導体用語などもでてくるため、なかなか理解がしづらいものです。
そこで今回は、半導体産業を牽引してきた「ムーアの法則」について、どのような意味を持ち、またどのような影響を与えてきたのか、そのほか進化を与えた集積回路(IC)についても最後におさらいとして簡単に解説していきます。
ムーアの法則とは?
ムーアの法則は、インテル創業者の一人であるゴードン・ムーア氏が、1965年に『半導体の性能が18か月で2倍になる』という経験則を提唱したものです。経験測とは、実際に経験した事柄から見出された法則のことを指します。
ムーアの法則・・・「p=2n/1.5」(p=倍速・n=年数)
上記がムーアの法則の公式です。この公式は、1.5年後(18か月)で半導体の性能が2倍にあがる、という意味を持ちます。具体的には、トランジスタの集積率が2年後には2.52倍、5年後には10.08倍、10年後には101.6倍となるわけです。
半導体の集積率はムーアの法則が提唱されて以来、法則通りに進化を遂げてきました。ムーアの法則によって、現在、私たちの身近な家電製品であるスマートフォンやパソコンが広く普及しやすい環境が作られ、仕事や生活への利便性も向上しています。

ムーアの法則による半導体集積回路(IC)の進化
ムーアの法則により、影響をもたらした半導体集積回路(IC)の進化は次のようなものがあげられます。
小型化・高機能化・低電力化:一つの同じ集積回路(IC)上に、膨大な数の半導体素子を搭載できるようになり、動作処理速度や消費電力を維持できるようになった。
低コスト化:一枚の基板上で、2倍の半導体素子が作られるため低コストに繋がった。
現在では時代のニーズ変化や、開発の難易度、小型化の限界などによってムーアの法則も次第に限界が語られるようになりました。
ただ長い間、ムーアの法則が半導体産業の発展を牽引しつづけ、社会やIT技術などへの進歩に繋がったことに変わりはありません。
半導体集積回路(IC)のおさらい
半導体集積回路(IC)について、最後にここで少し整理してみます。集積回路(IC)とは、半導体素子が一つの基板上に結合され、数千個や数千万個に集められたものを指します。どのような半導体素子があるのか、一例ではありますがみていきましょう。
| 半導体素子 | 特徴や役割 |
|---|---|
| トランジスタ | 増幅作用(弱い電気信号を強い電気信号に変換する) スイッチング(電気のon/offの切り替え) |
| ダイオード | 電気の流れを制御 (電気の流れを整える・電圧を一定にする・電圧の検波をする) |
| アクティブフィルタ | 高調波を抑制 |
| アンプIC | 電気信号を増幅 |
| PLD | 論理回路構造の変更や再定義 |
| メモリ | データの記録 |
| GPU | 画像処理装置 |
| MPU(CPU) | パソコンなどの頭脳部分にあたる (中央処理装置や中央演算処理装置と呼ばれている) |
トランジスタは、「ムーアの法則」で登場した半導体素子です。また、MPU(CPU)はインテルが世界初電卓用として使用し、パソコン内では頭脳的役割のほかデータ処理などさまざまな処理を行っています。
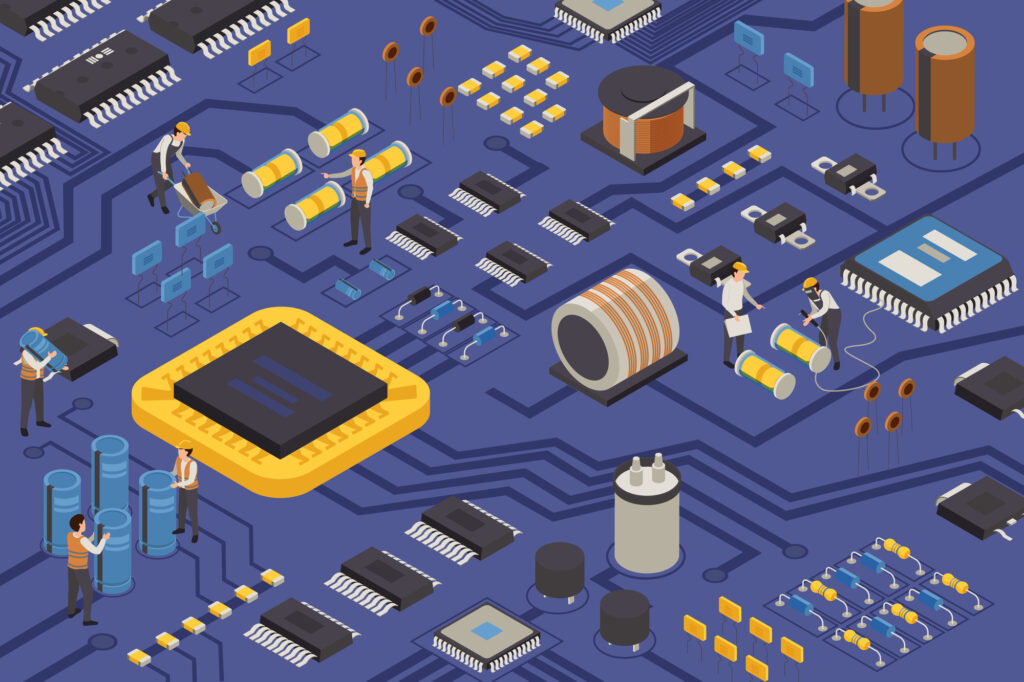
まとめ
今回は、「ムーアの法則」とはどのようなものなのか、影響を与えた集積回路(IC)の進化や、併せて集積回路(IC)のおさらいまで簡単に解説いたしました。
半導体産業を牽引してきたゴードン・ムーア氏による「ムーアの法則」、少し触れてみたことで半導体のおもしろさや、また違う視点から半導体製品を見るきっかけとなったのではないでしょうか。
半導体が日々進化を遂げるたびに、仕事や私生活においても変化をもたらします。いつの時代も私たちの身近にあり、そして今後もさまざまな面で半導体が支えとなってくれることでしょう。







